リンク切れてるっていう連絡をもらったので更新しておきました(2018/01/30)。
モデルにgoogle tasksのapiを使ってbackbone.jsでアプリをつくるチュートリアルを読んだ。
package.jsonのscriptsのセクションにstartがないのにnpm startでサーバーが立ち上がるのはなんでじゃろかー?って不思議だったので、ぐぐってみた。
npm startのデフォルトはnode server.jsらしい。

Backbone.sync
RESTfulなAPIじゃない場合とか他のライブラリを使いまわす場合どうするのかなと思って調べてみたらBackbone.syncを上書きすればいいらしい。modelのほうはいじらないでsyncでよろしくやればいいみたい。
Backbone.sync = function(method, model, options) {
var requestContent = {};
options || (options = {});
switch (model.url) {
case 'tasks':
requestContent.task = model.get('id');
break;
case 'tasklists':
requestContent.tasklist = model.get('id');
break;
}
switch (method) {
case 'create':
requestContent['resource'] = model.toJSON();
request = gapi.client.tasks[model.url].insert(requestContent);
Backbone.gapiRequest(request, method, model, options);
break;
case 'update':
requestContent['resource'] = model.toJSON();
request = gapi.client.tasks[model.url].update(requestContent);
Backbone.gapiRequest(request, method, model, options);
break;
case 'delete':
requestContent['resource'] = model.toJSON();
request = gapi.client.tasks[model.url].delete(requestContent);
Backbone.gapiRequest(request, method, model, options);
break;
case 'read':
request = gapi.client.tasks[model.url].list(options.data);
Backbone.gapiRequest(request, method, model, options);
break;
}
};

 数学的推論が世界を変える―金融・ゲーム・コンピューター (NHK出版新書 394)
数学的推論が世界を変える―金融・ゲーム・コンピューター (NHK出版新書 394) 関数プログラミング入門 ―Haskellで学ぶ原理と技法―
関数プログラミング入門 ―Haskellで学ぶ原理と技法― 数学ガール ゲーデルの不完全性定理 (数学ガールシリーズ 3)
数学ガール ゲーデルの不完全性定理 (数学ガールシリーズ 3)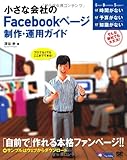 小さな会社のFacebookページ制作・運用ガイド (Small Business Support)
小さな会社のFacebookページ制作・運用ガイド (Small Business Support) スマートフォンデザインでラクするために
スマートフォンデザインでラクするために

 ワイド版 風の谷のナウシカ7巻セット「トルメキア戦役バージョン」 (アニメージュ・コミックス・ワイド版)
ワイド版 風の谷のナウシカ7巻セット「トルメキア戦役バージョン」 (アニメージュ・コミックス・ワイド版) 自分のアタマで考えよう
自分のアタマで考えよう ビジネスの成功はデザインだ
ビジネスの成功はデザインだ デュシャンは語る (ちくま学芸文庫)
デュシャンは語る (ちくま学芸文庫) 芸術起業論
芸術起業論 リーン・スタートアップ ―ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす
リーン・スタートアップ ―ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす
 HUNTER×HUNTER 19: No.19 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 19: No.19 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 20: No.20 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 20: No.20 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 21: No.21 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 21: No.21 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 22: No.22 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 22: No.22 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 23: No.23 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 23: No.23 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 24 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 24 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 25 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 25 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 26: NO.26 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 26: NO.26 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 27 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 27 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 28 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 28 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 29 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 29 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 30 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 30 (ジャンプコミックスDIGITAL)