19062011 life
なにげにドラッカーを読むのは初めてだったりする。経営者が読むもんだと思っていたので。
社会がどう変わるかという話ですね。モチベーション3.0なんかが語っている世界に近いです。
継続的に学習、教育の必要な社会になるのは間違いなく、知識労働者の資本とは知識そのものであり、知識社会と知識経済においては知識が主たる生産手段だと。
知識労働者として生きていくには3つのことを自答する必要がある。
- 自分の強みは何か、どのような強みを発揮できるか
- 何を期待してもらいたいか、いつまでに結果を出せるか
- そのためにはどういう情報が必要か
- 成熟産業に対する保護は無効
- 鉄道が生んだ心理的な地理によって人は距離を克服し、eコマースが生んだ心理的な地理によって人は距離をなくす。もはや世界には一つの経済、一つの市場しかない
- 製造の力では製品を差別しきれない
- たとえ世界一の研究所を持っていたとしても、業界の景色を変える技術や製品は出てこない、研究所は内側を向いているから
- 命令や管理の時代は終わった
- イノベーションとは、市場に追いつくために自分の製品やサービスを自分で変えていくこと
- 雇用関係は与件であってメンバーは変えられない。したがって、成果をあげるのは指揮者の対人能力
- 高齢化よりも少子化のほうが問題だ

 ネクスト・ソサエティ ― 歴史が見たことのない未来がはじまる
ネクスト・ソサエティ ― 歴史が見たことのない未来がはじまる 正社員は危ない! "リストラなう"を生き抜く方法
正社員は危ない! "リストラなう"を生き抜く方法

 アート・オブ・コミュニティ ―「貢献したい気持ち」を繋げて成果を導くには
アート・オブ・コミュニティ ―「貢献したい気持ち」を繋げて成果を導くには D・カーネギーの成長力
D・カーネギーの成長力

 Pro Puppet
Pro Puppet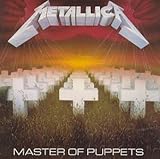 Master of Puppets
Master of Puppets フォーカル・ポイント
フォーカル・ポイント 本田直之「人を動かすアフォリズム」90
本田直之「人を動かすアフォリズム」90 ニューノーマル―リスク社会の勝者の法則
ニューノーマル―リスク社会の勝者の法則 マインドセット ものを考える力
マインドセット ものを考える力 自分ブランドの教科書
自分ブランドの教科書 脳が教える! 1つの習慣
脳が教える! 1つの習慣 野村再生工場 ――叱り方、褒め方、教え方 (角川oneテーマ21 A 86)
野村再生工場 ――叱り方、褒め方、教え方 (角川oneテーマ21 A 86) 高校生が感動した「論語」 (祥伝社新書)
高校生が感動した「論語」 (祥伝社新書) 人を動かす 新装版
人を動かす 新装版 勝てば官軍―成功の法則
勝てば官軍―成功の法則 ドラッカー名著集1 経営者の条件
ドラッカー名著集1 経営者の条件 客家大富豪 18の金言
客家大富豪 18の金言 話し方入門 新装版
話し方入門 新装版 ブライアン・トレーシーの 話し方入門 ー人生を劇的に変える言葉の魔力
ブライアン・トレーシーの 話し方入門 ー人生を劇的に変える言葉の魔力 誰とでも 15分以上 会話がとぎれない!話し方 66のルール
誰とでも 15分以上 会話がとぎれない!話し方 66のルール
 虹の風景 (青菁社フォトグラフィックシリーズ)
虹の風景 (青菁社フォトグラフィックシリーズ) 農はショーバイ!
農はショーバイ!