Python vs Clojure – Evolving « Best in Classをみてて、「ほう」となったので、手元のmacbookで。
t_seq.py
def count(n):
while n > 0: n -= 1
count(100000000)
count(100000000)
t_thread.py
from threading import Thread
def count(n):
while n > 0: n -= 1
t1 = Thread(target=count,args=(100000000,))
t1.start()
t2 = Thread(target=count,args=(100000000,))
t2.start()
t1.join()
t2.join()
t_mprocessing.py
from multiprocessing import Process
def count(n):
while n > 0:
n -= 1
t1 = Process(target=count,args=(100000000,))
t1.start()
t2 = Process(target=count,args=(100000000,))
t2.start()
t1.join()
t2.join()
結果
$ time python t_seq.py;time python t_thread.py;time python t_mprocessing.py
real 0m17.032s
user 0m16.886s
sys 0m0.067s
real 0m37.139s
user 0m29.756s
sys 0m23.039s
real 0m8.777s
user 0m16.973s
sys 0m0.083s
Clojureのほう
user=> (defn countdown [n] (when (pos? n) (recur (dec n))))
#'user/countdown
user=> user=> (time (doall (pmap countdown (repeat 2 100000000))))
"Elapsed time: 8164.085 msecs"
(nil nil)

 Essential Sqlalchemy
Essential Sqlalchemy
 プログラミングHaskell
プログラミングHaskell BUFFALO ネットワーク対応HDD LinkStation 1.0TB LS-CH1.0TL
BUFFALO ネットワーク対応HDD LinkStation 1.0TB LS-CH1.0TL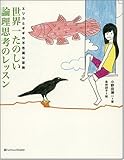 世界一たのしい論理思考のレッスン エリカとギギの不思議な冒険
世界一たのしい論理思考のレッスン エリカとギギの不思議な冒険 容疑者ケインズ (ピンポイント選書)
容疑者ケインズ (ピンポイント選書) 不確実性のマネジメント 新薬創出のR&Dの「解」
不確実性のマネジメント 新薬創出のR&Dの「解」 Essential Sqlalchemy
Essential Sqlalchemy 「ひらめき」の設計図
「ひらめき」の設計図