26012013 life
Facebookはローカルな関係をネットに投影しているだけなのであまり面白さを感じないんだけど、店舗持っているヒトには良いツールなのかもしれないなぁと思ったので読んでみた。というより佳肴 季凛さんのFacebookの使い方上手だなぁと思ったので、Facebookも面白そうだなと思ったという。
要するに美味しいものが好きなだけなんですが、、、
オンラインからオフラインに導く施策をO2Oっていうらしい(知らんかった)。
本書は入門者向けの構成かな、インサイトの見方くらいしか見るとこなかった。もう少し、ソーシャルな方向から考えてる本のほうが良かったかな。

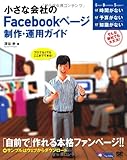 小さな会社のFacebookページ制作・運用ガイド (Small Business Support)
小さな会社のFacebookページ制作・運用ガイド (Small Business Support)

 ワイド版 風の谷のナウシカ7巻セット「トルメキア戦役バージョン」 (アニメージュ・コミックス・ワイド版)
ワイド版 風の谷のナウシカ7巻セット「トルメキア戦役バージョン」 (アニメージュ・コミックス・ワイド版) 自分のアタマで考えよう
自分のアタマで考えよう ビジネスの成功はデザインだ
ビジネスの成功はデザインだ デュシャンは語る (ちくま学芸文庫)
デュシャンは語る (ちくま学芸文庫) 芸術起業論
芸術起業論 リーン・スタートアップ ―ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす
リーン・スタートアップ ―ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす HUNTER×HUNTER 19: No.19 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 19: No.19 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 20: No.20 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 20: No.20 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 21: No.21 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 21: No.21 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 22: No.22 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 22: No.22 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 23: No.23 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 23: No.23 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 24 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 24 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 25 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 25 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 26: NO.26 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 26: NO.26 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 27 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 27 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 28 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 28 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 29 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 29 (ジャンプコミックスDIGITAL) HUNTER×HUNTER 30 (ジャンプコミックスDIGITAL)
HUNTER×HUNTER 30 (ジャンプコミックスDIGITAL) Think Simple―アップルを生みだす熱狂的哲学
Think Simple―アップルを生みだす熱狂的哲学

 こびとづかん 300ラージピース こびとの採集2 300-L338
こびとづかん 300ラージピース こびとの採集2 300-L338 MacBook 13MA25*.699.700.MB*の A1185 対応バッテリー
MacBook 13MA25*.699.700.MB*の A1185 対応バッテリー 電子書籍を無名でも100万部売る方法
電子書籍を無名でも100万部売る方法