Real World HakellのSTMの章がなんか消化不良だったのでなんかないかなぁと探したら、ビューティフルコードにSTMの章があったのを思い出したので、早速読んだ。
ちなみに英語のはここ
サンタクロース問題わかりやすい。ついでに動かしてみたけどControl.Monadもインポートしないと動かない@GHC6.12.3
module Main where
import Control.Concurrent.STM
import Control.Concurrent
import Control.Monad
import System.Random
meetInStudy :: Int -> IO ()
meetInStudy id = putStr ("Elf " ++ show id ++ " meeting in the study\n")
deliverToys :: Int -> IO ()
deliverToys id = putStr ("Reindeer " ++ show id ++ " delivering toys\n")
helper1 :: Group -> IO () -> IO ()
helper1 group do_task = do
(in_gate, out_gate) <- joinGroup group
passGate in_gate
do_task
passGate out_gate
elf1, reindeer1 :: Group -> Int -> IO ()
elf1 gp id = helper1 gp (meetInStudy id)
reindeer1 gp id = helper1 gp (deliverToys id)
data Gate = MkGate Int (TVar Int)
newGate :: Int -> STM Gate
newGate n = do { tv <- newTVar 0; return (MkGate n tv)}
passGate :: Gate -> IO ()
passGate (MkGate n tv) = atomically (do n_left <- readTVar tv
check (n_left > 0)
writeTVar tv (n_left-1))
operateGate :: Gate -> IO ()
operateGate (MkGate n tv) = do
atomically (writeTVar tv n)
atomically (do {n_left <- readTVar tv; check (n_left == 0)})
data Group = MkGroup Int (TVar (Int, Gate, Gate))
newGroup :: Int -> IO Group
newGroup n = atomically ( do g1 <- newGate n
g2 <- newGate n
tv <- newTVar (n, g1, g2)
return (MkGroup n tv))
joinGroup :: Group -> IO (Gate, Gate)
joinGroup (MkGroup n tv)
= atomically (do (n_left, g1, g2) <- readTVar tv
check (n_left > 0)
writeTVar tv (n_left-1, g1, g2)
return (g1,g2))
awaitGroup :: Group -> STM (Gate, Gate)
awaitGroup (MkGroup n tv)
= do (n_left, g1, g2) <- readTVar tv
check (n_left == 0)
new_g1 <- newGate n; new_g2 <- newGate n
writeTVar tv (n,new_g1,new_g2)
return (g1, g2)
randomDelay :: IO ()
randomDelay = do
waitTime <- getStdRandom (randomR (1, 1000000))
threadDelay waitTime
elf :: Group -> Int -> IO ThreadId
elf gp id = forkIO (forever (do {elf1 gp id; randomDelay}))
reindeer :: Group -> Int -> IO ThreadId
reindeer gp id = forkIO (forever (do {reindeer1 gp id; randomDelay}))
santa :: Group -> Group -> IO ()
santa elf_gp rein_gp = do
putStr "--------------------------\n"
choose [(awaitGroup rein_gp, run "deliver toys"), (awaitGroup elf_gp, run "meet in my study")]
where
run :: String -> (Gate, Gate) -> IO ()
run task (in_gate, out_gate) = do
putStr ("Ho! Ho! Ho! let's " ++ task ++ "\n")
operateGate in_gate
operateGate out_gate
choose :: [(STM a, a -> IO ())] -> IO ()
choose choices = do act <- atomically (foldr1 orElse actions)
act
where
actions :: [STM (IO ())]
actions = [do {val <- guard; return (rhs val)} | (guard, rhs) <- choices ]
main = do
elf_group <- newGroup 3
sequence_ [ elf elf_group n | n <- [1..10]]
rein_group <- newGroup 9
sequence_ [reindeer rein_group n | n <- [1..9]]
forever (santa elf_group rein_group)
で、なんでputStrLn使わないのかなぁとか思いつつ、自分でputStrLn使って書いたコードを実行したら
--------------------------
Ho! Ho! Ho! let's deliver toys
Reindeer 4 delivering toys
Reindeer 6 delivering toysReindeer 5 delivering toysReindeer 7 delivering \
toysReindeer 2 delivering toysReindeer 3 delivering toysReindeer 9 \
delivering toysReindeer 8 delivering toysReindeer 1 delivering toys
みたいに文字が出力された後に改行がずらずら出力されることがある。
あー!と思ってソースを見たら
putStrLn :: String -> IO ()
putStrLn s = do putStr s
putChar '\n'
という定義だった。というわけで、putStrじゃないといけない理由がわかった。
 ビューティフルコード
ビューティフルコード
Brian Kernighan,Jon Bentley,まつもとゆきひろ
オライリージャパン / ¥ 3,990 ()
在庫あり。






 これからの思考の教科書 ~論理、直感、統合ー現場に必要な3つの考え方~
これからの思考の教科書 ~論理、直感、統合ー現場に必要な3つの考え方~ ウェブで学ぶ ――オープンエデュケーションと知の革命 (ちくま新書)
ウェブで学ぶ ――オープンエデュケーションと知の革命 (ちくま新書)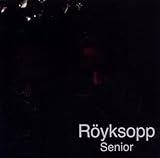 Senior
Senior どうぶつしょうぎ (日本女子プロ将棋協会公認)
どうぶつしょうぎ (日本女子プロ将棋協会公認) ビューティフルコード
ビューティフルコード Real World Haskell―実戦で学ぶ関数型言語プログラミング
Real World Haskell―実戦で学ぶ関数型言語プログラミング 一坪家庭菜園―狭い庭でもここまでできる
一坪家庭菜園―狭い庭でもここまでできる ケモインフォマティックス―予測と設計のための化学情報学
ケモインフォマティックス―予測と設計のための化学情報学